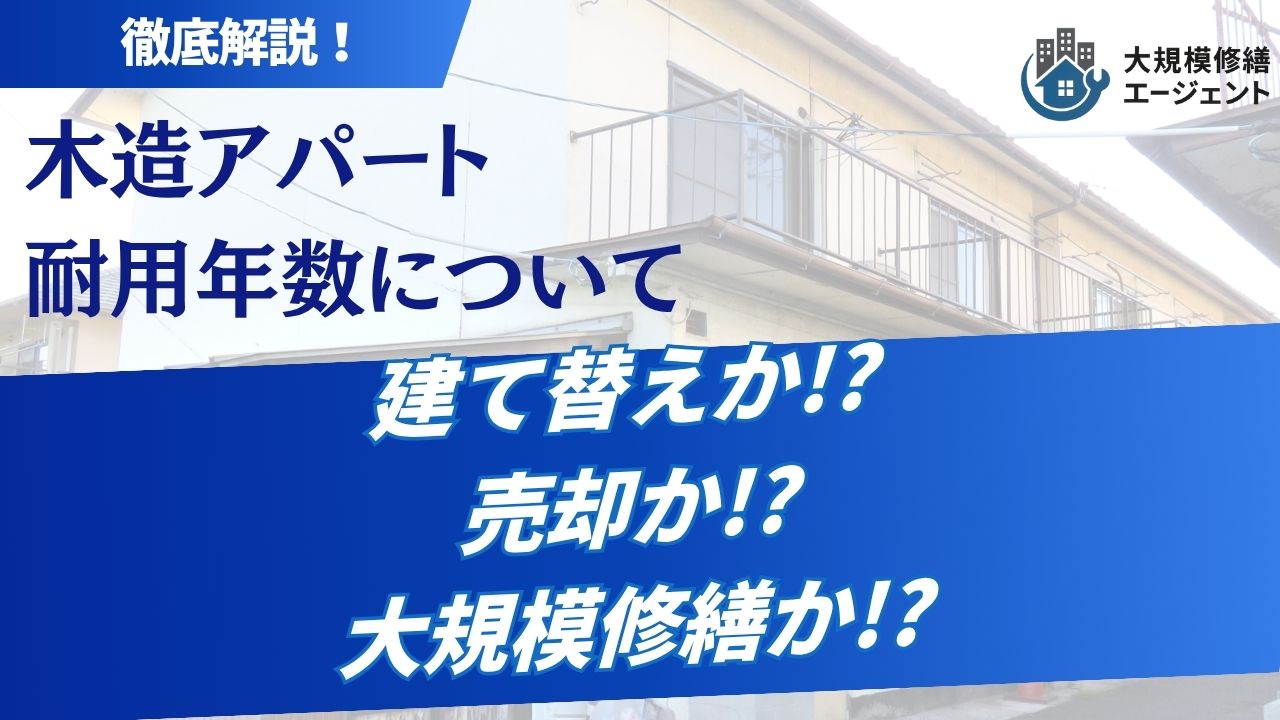アパート経営は20年以上にわたる長期での経営になります。長い期間、安全に確実に賃料収入を得るためには、実際に入居者が安心して住めるようにアパートの「耐用年数」について理解をする必要があります。
本記事ではアパートの耐用年数にまつわる疑問を払拭して、安心して長期的に安定した収入が得られるアパート経営のために、オーナーが知っておくべきことをまとめています。
この記事を読むと、以下のことがわかります。
また、修繕積立金に関するご相談は大規模修繕エージェントへご連絡ください。修繕積立金や収支計画の無料診断を行い最適な業者を紹介させて頂きます。
1.アパートの経営における法定耐用年数とは

アパートの法定耐用年数は構造別に基準が設けられています。
設けられた基準の年数がないであればアパートの資産かちは税務上残りますが、法定耐用年数を過ぎた場合は、税務上の資産価値は消滅します。
建物の寿命は、「法定耐用年数」(ほうていたいようねんすう)を過ぎたからといって、すぐに尽きるわけではありません。
この「法定耐用年数」というのは、主に税務上の計算(減価償却)のために法律で定められた目安の年数です。
そのため、定期的にリフォームや修繕といった適切なメンテナンス(お手入れ)さえ行っていれば、実際にはこの年数を超えても、はるかに長く建物を使い続けられるケースがほとんどです。
建物は時間が経てば必ず古くなったり傷んだりします(経年劣化)。こうした点にきちんと対処していくことで、法定耐用年数以上、安全で快適に使用することが可能になります。
最適なタイミングで安心した工事を実現するなら大規模修繕エージェントへ
2.木造アパートの法定耐用年数
木造アパートの法定耐用年数は22年です。
木造アパートは建物の構造体に木材が使用されているため、加工がしやすいなどの柔軟性がある一方で、燃えやすく鉄骨やコンクリートと比較して虫害や腐りやすい特徴がある点から耐用年数は鉄骨造や鉄骨コンクリート造の建物と比較すると短くなっています。
比較をすると以下の通りです。

どの構造の建物も法定耐用年数よりも長く寿命があるので、法定耐用年数を超えたアパートであっても、すぐに建て替えなどせずに、修繕などのメンテナンスをしながら長期間使用していきましょう。
3.耐用年数が過ぎた木造アパートに起きる4つの経営デメリットについて
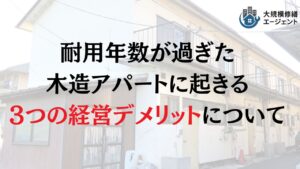
法定耐用年数の22年が過ぎてしまった木造アパートに起きる、経営上のデメリットをまとめました。
- 修繕費用がかさみ収支が悪化する
- 新規に融資が下りない
- そのままでは売却も難しくなる
3-1修繕費用がかさみ収支が悪化する
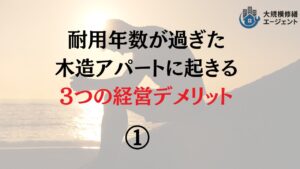
法定耐用年数である22年を超え、アパートローンが完済すると、家賃収入から経費を差し引いた分がそのまま手取り収入となり、キャッシュフローは大きく改善します。これはアパート経営における一つの大きな節目です。
しかし同時に、築年数が経過するほど「支出(修繕費)」が増加し、「収入(家賃)」が減少しやすいという、相反する傾向が強まる時期でもあります。この「収支バランスの変化」をどう管理していくかが、今後の安定経営の鍵となります。
具体的には、以下のような変化が想定されます。
- 建物の経年劣化と突発的な支出 耐用年数を過ぎた建物は、屋根や外壁など、これまで問題がなかった部分にも経年劣化が表れ始めます。雨水の染み込みによる躯体への影響や、台風などでの破損リスクは高まる傾向にあり、突発的かつ高額な修繕費が発生する可能性を考慮する必要があります。
- 設備・内装の老朽化と入居者ニーズの変化 建物内部でも、エアコン、給湯器、配管といった設備は老朽化が進みます。これらは入居者の快適性に直結するため、不具合や古さが目立つと、競合する新しい物件と比べて見劣りし、入居者満足度の低下や退去につながることも考えられます。
- 空室リスクと賃料設定 建物の外観や間取りが時代に合わなくなると、空室を避けるために賃料を下げて対応する必要が出てくるかもしれません。家賃収入が緩やかに下落する中で、修繕費の負担が重なると、当初想定していた収支計画との乖離が生まれる可能性があります。
ローン完済による手取り収入を安定的に確保し続けるためには、こうした「築年数と共に高まるリスク」を客観的に把握することが重要です。 いつ、どの程度の修繕が必要になりそうか、競合と比較して物件の魅力をどう維持していくか。感情論ではなく、長期的な経営計画(キャッシュフロー計画)の視点で、建物の現状と向き合い、対策を検討していく時期と言えるでしょう。
3-2新規に融資が下りない

木造アパート経営において、大規模な修繕は法定耐用年数である「築22年」を迎える前に計画し、実行を検討すべきです。
なぜなら、修繕費用のためにアパートローン(事業用ローン)を利用しようとしても、多くの金融機関が「法定耐用年数」を融資の可否を判断する重要な基準にしているからです。木造の場合、築22年を超えた物件は融資審査に通らないことが多くなります。
もし築22年を過ぎてしまうと、50~100万円単位の比較的小さなリフォーム費用でさえローンが下りず、オーナーは全額を自己資金で用意する必要に迫られます。手元に資金がなければ修繕は先延ばしになり、その間に建物の傷みは急速に進みます。結果として、住みづらさを感じた入居者の退去を招くという悪循環に陥ってしまいます。
このような事態を避け、アパート経営を安定させるためにも、まだ融資が受けやすい「築22年以内」に必要な修繕計画を見直しておくことが極めて重要です。現状の経営を継続するパターンと、将来的な建て替えのパターンを具体的に比較検討し、早めに経営計画を立て直しておく必要があります。
3-3「そのまま」では売却も難しくなる

法定耐用年数である22年を超えた木造アパートは、「そのままの状態」で売却しようとすると、買い手を見つけるまでにかなりの時間と労力がかかります。
最大の理由は、金融機関が耐用年数を過ぎたアパートへの融資に非常に消極的であるためです。結果として、買い手は「現金一括で購入できる方」(多くは企業かプロの不動産投資家)に限定されてしまいます。
「買い叩かれる」リスク
不動産のプロが、あえて築古物件を現金で購入する場合、その目的は「建て替え」か「安く買ってリフォームし、より高い収益を得る」ことです。 どちらにせよ、彼らは物件の老朽化や現在の収益性の低さを理由に、厳しい価格交渉(値下げ)を行ってくるでしょう。
なかなか買い手がつかない場合、値下げ交渉に応じざるを得なくなり、オーナー様が期待している金額を大きく下回る可能性が高くなります。
4.木造アパートの耐用年数が過ぎたときの3つの対処方法

4-1.アパートを建て替える
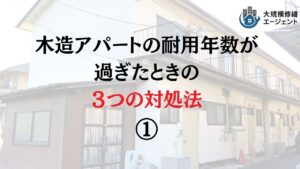
アパートの建て替えは、建て替え後も安定した経営が見込める場合に検討すべき選択肢です。
なぜなら、建て替えは多額の初期費用がかかるだけでなく、入居者がいる場合は立ち退き料の支払いが必要になることがほとんどだからです。
具体的に「安定経営が見込める要素」としては、立地条件が良く入居者が集まりやすい、あるいは既存のアパートローンを完済している(資金計画が立てやすい)といったケースが考えられます。
したがって、大規模修繕か建て替えかで迷う場合、まずは立ち退きの流れや必要な資金計画について、不動産会社や金融機関にしっかり相談してみることをお勧めします。
4-2.アパートを売却する
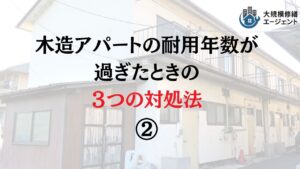
法定耐用年数が過ぎたアパートでも、土地の価値を基準に価格設定し、「建物ごと」売却することをお勧めします。
なぜなら、建物の価値がゼロと見なされても、買い手は「土地を担保に」融資を受けられる可能性が残っているためです。
特に、入居者がいる「オーナーチェンジ物件」として売却するのが効果的です。買い手にとっては、購入後すぐに家賃収入(キャッシュフロー)が見込めるため、収益性を判断しやすく、前向きに購入を検討しやすいという大きなメリットがあります。
売却は耐用年数超過前が理想ですが、過ぎた場合でも「土地の担保価値」と「現在の収益性」を明確にすることで、買い手が見つかる可能性は十分にあります。
4-3. アパートをメンテナンスする
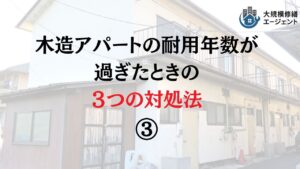
まず、大規模修繕(リフォーム)で物件の価値を高める方法があります。
なぜなら、古くなった部分を刷新することで、物件の魅力を回復させ、収益性を改善・維持できるからです。
例えば、外観や設備を一新すれば、入居者にとって魅力的になり空室対策につながります。家賃の維持、あるいは将来的に「優良な収益物件」として売却しやすくなることも期待できます。
これは「資産として、まだ活用し続けたい」場合に最適な選択肢です。ただし、費用対効果(いくらかけて、どれだけ収益が上がるか)をしっかり計画することが重要になります。
5.資産価値を守るため、今オーナーが取るべき「二つの選択」
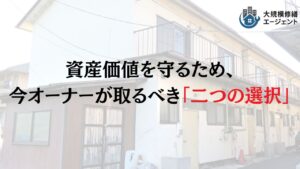
所有するアパートの資産価値を維持・向上させるため、オーナー様は将来的に「建て替え」か「修繕・リフォーム」かという大きな選択を迫られます。
しかし、近年、その選択の前提が大きく変わりました。建築資材や人件費の著しい高騰により、「建て替え」を実行するには莫大なコストがかかり、採算性を考えると現実的な選択肢とは言えなくなりつつあります。
建て替えという選択が困難になった今だからこそ、資産価値を守るために真剣に検討すべきは「大規模修繕による物件の再生」です。
選択肢①:大規模修繕

建物の経年劣化に対応する「大規模修繕」は、単なる維持管理にとどまりません。同時に時代に合った間取りや設備(※可能な範囲でのリフォーム・リノベーション)へ更新することで、物件の魅力を高め、入居率と収益性(家賃)の改善を図ります。
これにより、オーナーご自身が優良な収益物件として長期保有し続ける道が拓かれます。
また、仮に売却を検討する際も、単なる「古い物件」ではなく、「融資はつきにくいが、高利回り(または満室経営)が期待できる再生済み物件」として、次の投資家へ高値で売却できる可能性を高めることができます。
選択肢②:戦略的な売却

もし大規模修繕を行わず、現状のまま売却しようとすれば、その道は厳しくなります。
買い手からは「建て替え用地」として見なされ、近隣の土地相場から建物の解体費用を差し引かれた価格で買い叩かれるか、あるいは「大規模なリフォーム前提の物件」として、修繕費用を大幅に見込んだ安い価格でしか売却できない可能性が高くなります。
最も避けるべき「そのまま放置」というリスク
いずれの選択をするにせよ、最も避けなければならないのは「そのまま放置」することです。
建て替えが非現実的な状況で、大規模修繕も行わなければ、物件の劣化は進み、空室が増え、収益性は悪化の一途をたどります。そうなってからでは、売却しようにも買い手がつかず、資産価値は下がり続けます。
耐用年数が近づく中、建て替えという選択肢が現実的でない今だからこそ、計画的な大規模修繕こそが、オーナー様の大切な資産価値を守るための最も重要かつ現実的な戦略なのです。
大規模修繕の業者選びにお悩みの場合
『大規模修繕エージェント』なら、審査を経た優良業者に一括で見積もり依頼が可能。手間なく最適なプランを比較できます。まずは無料見積もりから。